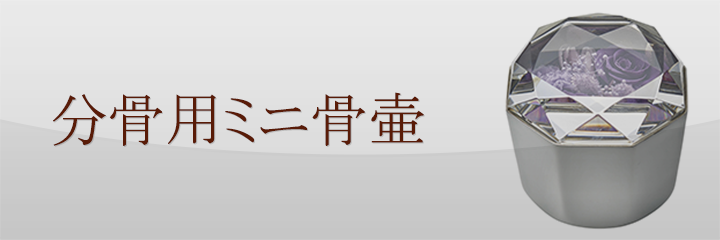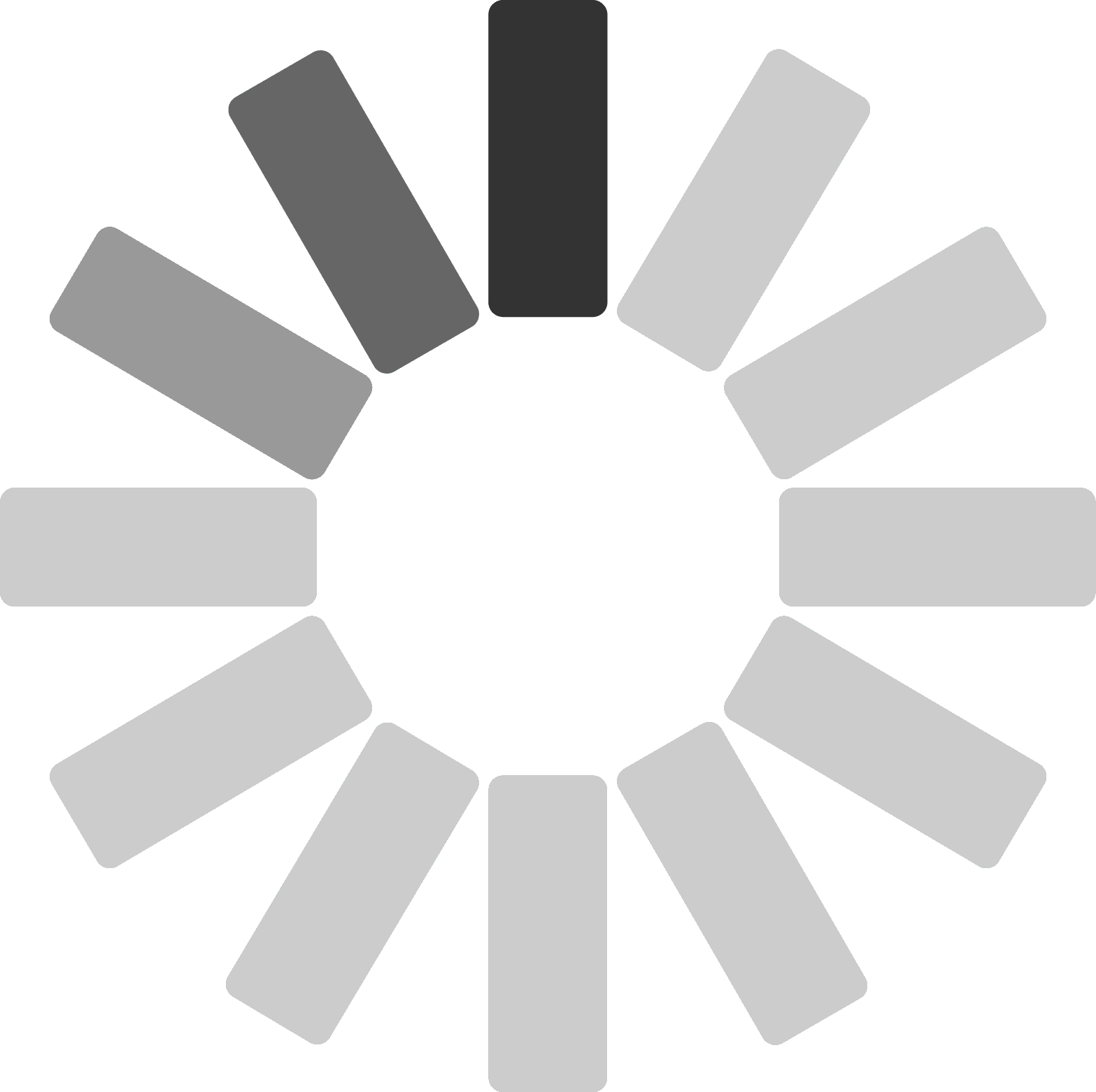お焼香の作法
お焼香の仕方は宗派などによ って違いがあ りますが、 基本的には以下の流れで行います。
1
遺族に一礼して焼香台のある仏前に進みます。
ご本尊と遺影を仰ぎ頭を下げて黙礼します。
2
右手で香をつまみます。
3
額のところまで押しいただきます。
(浄土真宗では押しいただきません)
4
香炉に静かにくべます。
これを宗派で決められた回数行うのですが、二回目からは額でおしいただく必要はありません。
※会葬者が多い場合、焼香は一回だけ行うことが、宗派問わず慣例化しているようです。
5
合掌礼拝します。
最後に遺族に一礼し、退きます。
お焼香の意味

仏教では、お葬式をはじめ、さまざまなご法要の折に必ずお焼香をします。
これにはお仏前を荘厳することによって敬虔な心をささげるという意味があります。
香は人の気持ちを快くするものですが、それと同時に芳香によって身心を清めるといった意味もあります。
香は仏教だけでなくキリスト教(カトリ ック)の葬儀でも、前夜式などで用いられているようです。
普通、近親者の焼香は葬儀式の時間内に行われ、一般会葬者の焼香は告別式開始と同時にはじめられます。

お数珠のかけかた
お数珠はもともと、お経やお題目をあげる時にその数をかぞえる法具でした。
今ではお経やお題目を唱えたり、 仏さまを礼拝する時に手にかけてお参りします。
お数珠は持っているだけで功徳があるとされ、 普通108の珠からできています。
これは、108の煩悩を退散・消滅させる功徳があるからだと言われていますが、珠の数はこのほかにも、108の10倍の1080のものから1/6の18のものまでさまざまあります。
形式については宗派によって若干の違いがありますので、求められる時に確認したほうがよいでしょう。
また、お数珠のかけかたも宗派によって異なります。

含掌のしかた
合掌は仏さまを尊び、供養する気持ちをあらわしたものです。
一説によれば、右手は仏さまを表し、左手は私たち凡夫を表すと言います。
手を合わせることによって仏さまの境地に私たちが近づけるというのです。
いずれにせよ、掌を合わせることによって心が落ちつき、精神が安定するのではないでしょうか。
合掌のしかたは、まず、指と指の間を離さずくっつけて、掌をピッタリと合わせます。そして、位置としては胸の前に、胸にはつけないで少し前に出します。
掌の角度は45度くらい。肘は張らず、脇も力を入れて締める必要はありません。肩の力を抜くようにすればよいでしょう。
厳密に言えば合掌にもいくつかの形があるのですが、この形がもっとも代表的なものです。