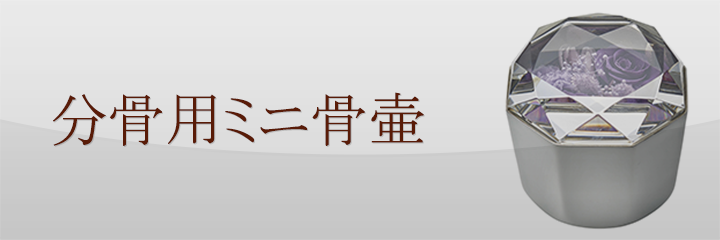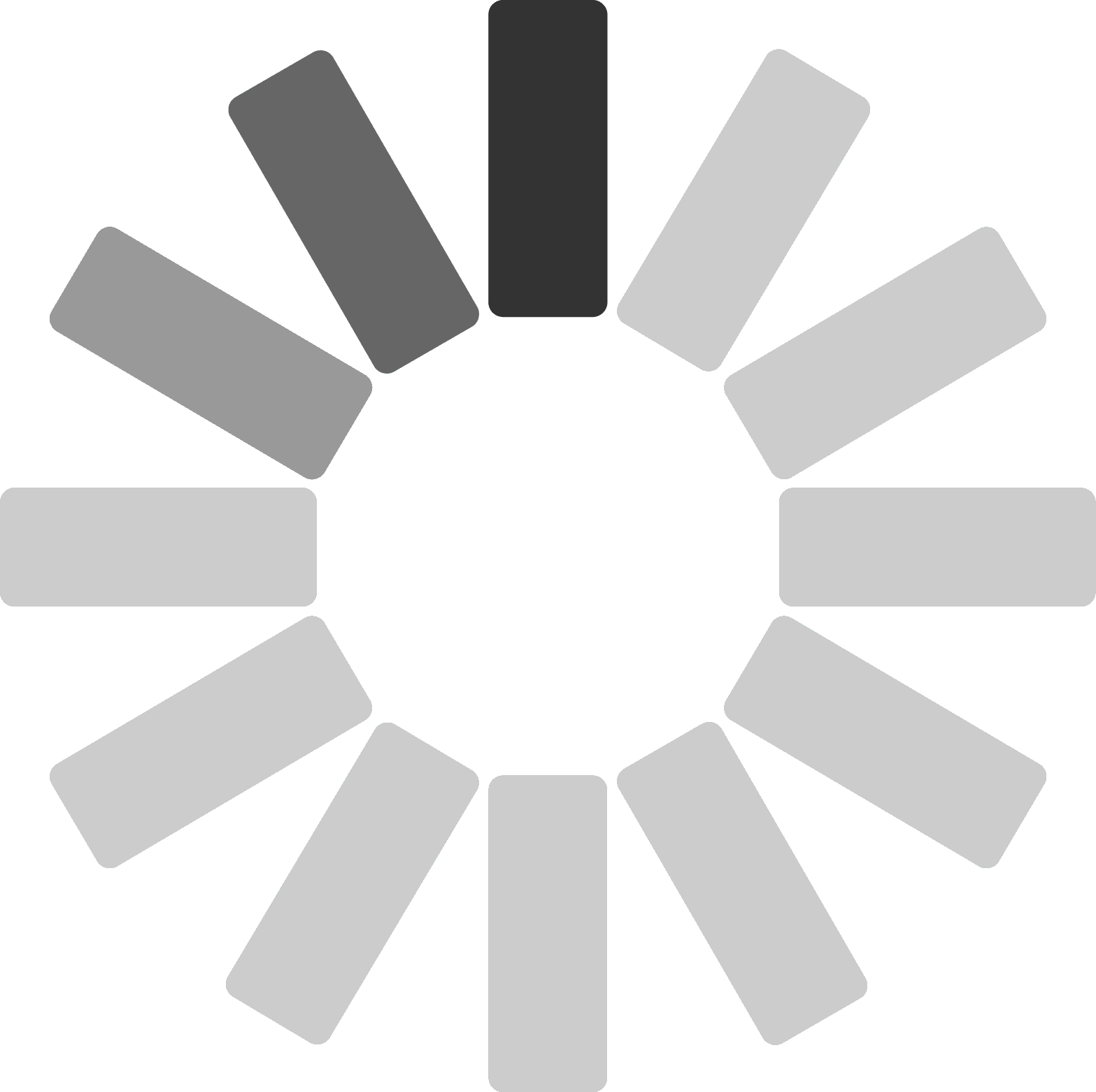法事とは、亡くなられた方のご供養をする仏教の儀式の一つです。
参加する側としては特に意識していなかった方も、主催する側になったら「法事って何をすればいいの?」と感じる方も多いのではないでしょうか?
今回は初めてでも安心して法事を行えるよう、ルールや準備するものについてわかりやすく解説していきます。
法事を行うタイミングは?
一般的には初めての法事は49日が該当することが多いです。
お葬式が終わったばかりで、手続きごとを済ませたばかりだというのに、ご法事の準備もしなければならず、葬儀後の喪主様の仕事は大変です。
早めに準備しましょう。
準備すること
法事の日時を決めましょう
お寺様への早めの予約が必要です。
まず日程を決めるのですが、実際の49日の日に近い日で、参加者の都合がつきやすい土日祝日を選ばれる方が多いです。
例えば、実際の49日が3月15日でもその前の3月10日の日曜日を選ぶという具合です。
まず参加していただきたい親族や知人に都合を聞きましょう。
そしてご自分の希望日を菩提寺様に伝え、都合を合わせましょう。
お寺様は法事が土日に集中するので必ずしも自分の希望日時が叶うとは限りません。

出席者の人数、食事する場所を決めましょう
食事の業者や会場を調べておきましょう。早めの予約が必要です。
往復ハガキや電話で法事に招待する方の出欠席を確認しましょう。ハガキは葬儀社様が持っている場合があります。(塔婆、お花、盛篭をあげてくれる人の案内もこのハガキに記載します)
次に招待客の人数を考えて、食事をする場所を仮予約を入れておくと良いでしょう。
最近は会食はせず、お弁当持ち帰りの法事も増えてきました。
食事の会場はお寺やホテル、レストランなど様々です。あまり離れた場所ならマイクロバスが必要になる場合もあります。
食事の会場によっては席順も考えておきます。ご住職様が参加される場合は上座となり、親族は下座になります。

お花、引き物の準備をしましょう
当日の出席者人数がほぼ決まりましたら、当日に手渡す引き物を手配します。
法事の引き物を扱う業者は返品が効く場合が多いので、予め返品の可能性も言っておくと良いです。
会場にはお花や供物、盛篭等を手配します。お寺で行う場合は住職様に聞きましょう。

霊園やお寺に出入りの石材屋さんに連絡しましょう
納骨がある場合、霊園やお寺に出入りの石材屋さんに連絡します。 当日の納骨時間の予約や、何を持っていくか(お線香・ローソク・ライター・お花など)教えていただきます。
位牌や仏壇の手配をしましょう
本位牌や仏壇の手配をします。 お仏壇をお持ちでない方はこの機会にお求めになった方が良いでしょう。 ご家庭の中のどこに安置するかを決め、サイズを考え、宗派を確認してから求めます。 お仏壇やお位牌は納期がかかりますので仏壇店によく相談して、49日までに間に合わせましょう。
法事当日の持ち物
当日、持参するものを再確認しましょう。
お骨、白木位牌、お花、供物、遺影(写真)、線香、ローソク、本位牌、仏壇の本尊(新しく用意した場合)など。
高齢の方が一人で持ち運ぶには数が多いです。お願いできたら参加者に手伝って頂きましょう。
礼服や黒ネクタイ、黒靴下、念珠なども当日に慌てないように準備します。
お布施も用意します。ご法事のお布施(志)と本位牌への魂入れのお布施袋(入魂料)は分けて用意して下さい。
石材屋さんやお手伝いしていただいた方に寸志も用意した方が良いかもしれません。

種類も多くて悩みがちなお線香・ローソクのおすすめ

デザイン、お色味、大きさも豊富にご用意しております

宗派に関係なくご利用いただける念珠をご用意しております
食事の席の献杯あいさつ
当日の食事の席で献杯のあいさつを喪主がする必要があります。
簡単に短い内容を考えておきましょう。
例) 本日はお忙しい中、おつき合いを頂きましてありがとうございました。父も安心していることと思います。
この席では、私たち家族が知らなかった父の想い出話などをお聞かせいただければと思っております。
まずは、献杯をさせて頂きたいと思いますので、ご唱和をお願いします。献杯。
法事当日
当日、必要なものを持参し、会場には30分前に着き参加者をお迎えしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以上が一般的な49日法要の段取りとなります。
法要とは他にも3回忌、7回忌、13回忌法要などがあります。故人を偲ぶとともに親族との親交や絆を深め温めるとても良い機会です。
喪主様には大変な気遣いと負担を伴いますがご法事を準備することも故人様への供養でもあり、参加者にも良い人生の節目になるものです。
できる限りのことをいたしましょう。